実技講習会参加者の声①
2025年04月11日にsmartsolutionさんが掲載
どのような悩みや目的で講習会に参加しましたか?
開業し、日々患者様と接する中で、主訴ではないものの食欲不振や不眠を訴える方が一定数居ることに気づきました。しかし、筋に対する治療はできても、内臓に対する治療の知識が乏しかったため、それを学ぶため反応点治療講習会に参加しました。
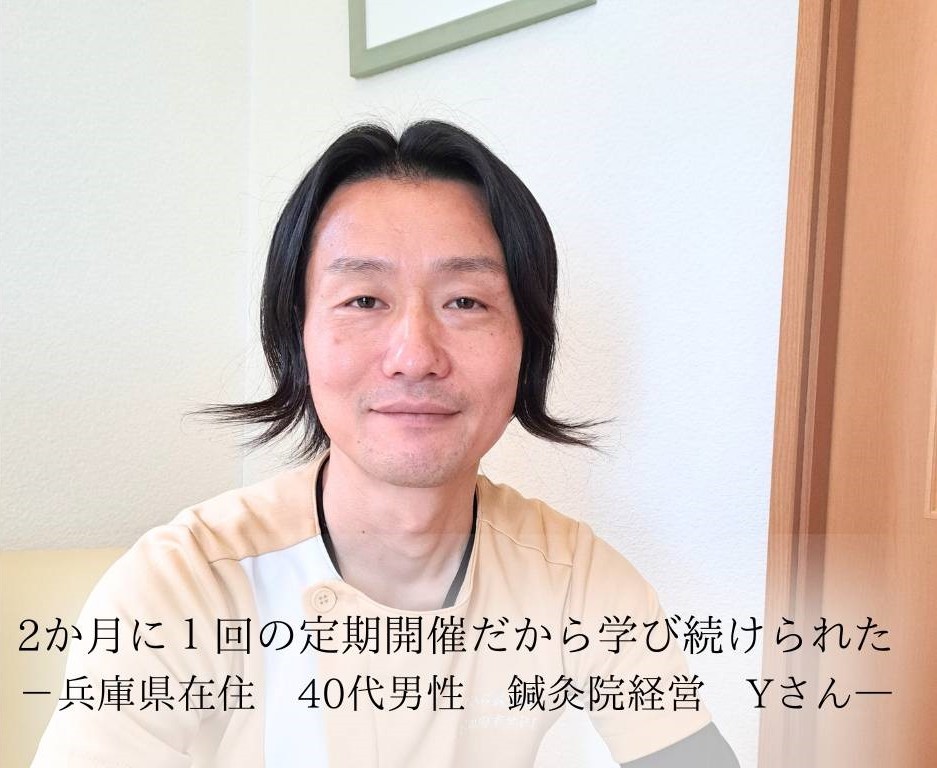
講習会参加前に不安だったことはありますか?
反応点治療についてはほぼ無知でしたので、不安や疑問はたくさんありました。反応点治療がどれくらい内臓不調や不定愁訴に対して効果的なのか?また、すでに反応点治療を行っている院にはどのような症状での来院が多くて、どの程度症状改善しているのか?など、「治療効果」や「実績」が知りたくて、鍼灸専門学校時代の同級生で反応点治療を行っていらっしゃる先生をたずねて、お話を聴かせていただきました。
あと、反応点治療を習得したとして、急に治療法が変わると既存患者様が違和感を感じたり
「今までの治療の方が良かった」とならないかという不安はありました。
その不安は講習会に参加してみてどう変化しましたか?
解剖学と生理学に基づいた治療理論で、非常にわかりやすかったため、「これは続けて学んでいけば臨床に活かせる!」と感じました。 ただ、実技練習の「触診」が独特で、それまで硬結を探すために押さえ込むように触診していた私には難解でした
講習会で特に役に立った内容や印象に残ったことを教えてください。
反応点の基礎理論です。なぜ反応点が現れるのか?なぜ筋緊張が起きるのか?はりや灸をすればそれらがなぜ改善するのか?といった仕組みが、解剖学と生理学に基づいた理論となっています。なので理解しやすい。そして、患者様にも説明しやすい。と思います。
講習会に参加して、考え方や行動にどんな変化がありましたか?
腰痛には委中、肩コリには合谷、というような固定概念がなくなりました。触診して反応点を探す。そしてなぜそこに反応点が現れているのか、それは何の反応点なのか、腰痛や肩こりとどう関わっているのか、などを考えるようになりました。1本ずつのはりに、解剖学や生理学に基づいた理由ができました。なので、患者様にも「こういう理由があってここにはりをしますね」という説明もできるようになりました。
講習会後に実際に取り組んでいることはありますか?
講習会で学んだことを、臨床や練習で使ってみるようにしました。来院頻度が高い患者様から「先生、触診のやり方が変わりました??」と聞かれたこともありましたし、「坐骨神経痛なのに、まずおなかを触るんですか??」と不思議がられたこともありました。ここぞとばかり、反応点治療の仕組みについて、極力専門用語を使わずに説明すると、意外と患者様も受け入れてくださいました。
この講習会をどんな人におすすめしたいですか?
偉そうに聞こえたらすいません。
「自分の治療に自信が持てていない鍼灸師・鍼灸学生」におすすめしたいです。
私は学生時代は脈診や八綱弁証、背候診などに興味があり学んでいました。ただ、卒業しても「自分の治療はこうなんだ!」という確固たる自信が持てずにいました。
反応点治療は私にとっては、とにかく理論がわかりやすかった。なので学び続けることができたんだと思います。「1つ、筋の通った治療」を身に着けたいとお考えの方は講習会に参加してみるのもいいのではないかと思います。
講習会に対する率直な感想やメッセージがあれば教えてください。
2か月に1回、定期開催されているのが良いと思います。講習会で学んだこと、例えば「独特な触診」を、次の日から臨床や練習で使ってみる。すると、「あれ?講習会の時はコツを掴んだと思ったのに、全然わからない」とか「これはたぶん胃の反応だな」など、失敗と成功の体験をする。その体験を持って2か月後の講習会に参加し、講師の先生に質問したり、実技をサポートしてもらったりすることで次の段階へ進む。この繰り返しで徐々に反応点治療を習得できたと感じています。

